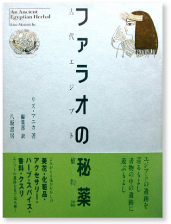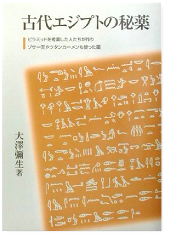エジプト
ファラオの秘薬
古代エジプトとはB.C.3100頃~B.C.30の古代のエジプトのこと。亜麻はこの頃メヒー(mHy)と呼ばれていました。 ミイラを包む布として使われていたり、エジプト第19王朝(B.C.1293~ B.C.1185)のテーベ第1号墓の死後の理想郷を描いた壁画に、 この墓に眠るセントジェイム夫妻が亜麻を育てる姿が描かれていたりと、 現存する資料からもエジプトでは古代から亜麻が利用されていたことが解ります。 古代エジプトの植物利用を紹介した「ファラオの秘薬ー古代エジプト植物誌」や、 同時代の薬学を紹介した「古代エジプトの秘薬」には、最古の医学文献と言われるエーベルス古文書をはじめ、 古代からの処方が載っており、その中にアマニの記述もあります。 「ファラオの秘薬ー古代エジプト植物誌」より「アマ」の解説の一部をご紹介します。
旧約聖書
アマはエジプトではずいぶん早くから栽培されている。出土する繊維がそのことを物語っている。亜麻仁油が登場する最も古い記録は、プトレマイオス王朝時代からのものである。だが、実際には食用油や灯油としてもっと古くから使用されていたことは間違いない。医薬としては、外用にされていただけのようである。アマの葉、タイガーナッツ、ある液体、それに未同定の材料から座薬を作り、肛門の腫れ(痔病か?)に用いていた。そして、お腹の熱は次のような薬で和らげていた。
アマの先端につく果実(1)、発酵した植物汁液を患者のお腹の上に置く。(E 179)(※1)
手足の爪先に施す包帯薬は、黄土、亜麻仁、エジプトイチジクの不明の一部分、蜂蜜、油か脂肪を材料として作られた(H 187)(※2)。亜麻仁油で作る湿布薬は、実際に痛みを緩和し、傷や化膿を治すのである。プロスペロ・アルピーニは、亜麻仁を鎮痛剤として服用する基本薬の成分の一つに挙げている(Medicine,266)(※3)。亜麻仁は、コプト人の処方に一か所だけ出ており、それはsirと呼ぶ病気を治療するためのものだった。すなわち、亜麻仁、イチジク、ゴム、蜂蜜で作るもので、患者に服用させたのである「が、患者はその後でイチジクの汁液を飲まなければならない」ということだった(Ch 22)(※4)。
- (「ファラオの秘薬ー古代エジプト植物誌」より)
- ※1:P.Ebers エーベルス古文書(B.C.1550頃)
- ※2:P.Hearst ハースト医学古文書(B.C.1550頃)
- ※3:1561-4年にエジプトに住んでいたベネチアの医師プロスペロ・アルピーニによる著作
- ※4:P.Chassinat 9世紀には成立していたコプト語の資料